感情労働とは、顧客対応などにおいて、特定の感情を適切に表現したり、不適切な感情を抑制したりすることが求められる労働のことです。この労働形態は、肉体労働や頭脳労働とは異なる、精神的な負担を伴うものとして認識されています。
感情労働は、サービス業、接客業、医療・介護業界など、人と接する機会が多い職種で多く見られます。例えば、客室乗務員、飲食店スタッフ、看護師、コールセンターオペレーターなどが該当します。これらの職業では、顧客の満足度を高めるために、常に笑顔で丁寧な対応を心がけることが求められます。しかし、時には理不尽なクレームや要求に対応しなければならないこともあり、精神的なストレスが蓄積されやすいという問題があります。
感情労働によるストレスを軽減するためには、企業による従業員へのサポートが重要です。例えば、ストレスチェック制度の導入、相談窓口の設置、カウンセリングの実施などが挙げられます。また、従業員自身も、趣味や運動など、ストレス解消になるような活動を取り入れることが大切です。
感情労働は、今後ますます増加していくと予想されています。企業は、感情労働の特殊性を理解し、従業員が心身ともに健康に働けるよう、適切な対策を講じる必要があります。
従来は肉体労働、頭脳労働という単純な二項分類において、感情労働は頭脳労働の一種としてカテゴライズされてきました。しかし一般的な頭脳労働に比べ、人間の感情に労働の負荷が大きく作用し、労働が終了した後も達成感や充足感などが得られず、ほぼ連日、精神的な負担、重圧、ストレスを負わなければならないという点に感情労働の特徴があります。
感情労働に従事する者は、たとえ相手の一方的な誤解や失念、無知、無礼、怒りや気分、腹いせや悪意、嫌がらせによる理不尽かつ非常識、非礼な要求、主張であっても、自分の感情を押し殺し、決して表には出さず、常に礼儀正しく明朗快活にふるまい、相手の言い分をじっくり聴き、的確な対応、処理、サービスを提供し、相手に対策を助言しなければなりません。つまり相手に尊厳の無償の明け渡しを半ば強制される健全とは言いがたい精神的な主従関係や軽度の隷属関係の強要になります。年功序列や接客業など、こちらの生活や人生が相手の判断で左右される職種において発生しやすいと思います。
感情労働は顧客に対して自発的な喜びや親愛、誠実さ、責任感などのイメージを与えるように「心の商品化」が要求されます。これってとても大変な事だと思います。感情労働における応対術には「表層演技」と「深層演技」があると言います。表層演技とは愛想笑いやお世辞など、自分の感情と無関係に他者に示す演技であり、接客業以外でも日常的に見られるものです。しかし、自己の内面にストレスが生じた状態で表層演技を行っても見透かされる場合もあります。プロの技術とも言える深層演技とは、自己の感情を生成の段階でコントロールすることで内面と外面の統一性を図り、たやすく装えるようにする技術であり、いわゆる「真心のこもったサービス」とは表層演技と深層演技が合致した状態で生起されるでしょう。
Youmeiの妻は銀行で窓口業務を遂行しています。妻からは様々なお客様が居る事を聞いております。ヤクザ調の方や真夏にサンタクローススタイルで来店される方等、想像を絶する程に特異なお客様がいらっしゃる様です。
近年、カスハラ行動が問題視されています。カスハラとは、カスタマーハラスメントの略で、顧客からの過度な要求や理不尽な言動によって、従業員の就業環境が害される行為を指します。単なるクレームとは異なり、要求の内容や手段・態度が社会通念上不相当なものである場合に、カスハラと判断されます。
①.
暴言・脅迫
従業員に対して、大声で怒鳴ったり、脅迫的な言葉を浴びせたりする行為.
②.
不当な要求
サービス内容の範囲を超えた過度な要求や、本来必要のないものを執拗に要求する行為
③.
長時間にわたる拘束
従業員を長時間拘束し、対応を強要する行為
④.
土下座の強要
些細なミスに対して、土下座を強要する行為
⑤.
SNSでの誹謗中傷
インターネット上で、従業員や企業を誹謗中傷する行為
カスハラは、感情労働に携わる従業員に大きなストレスを与える問題です。カスハラは、従業員のメンタルヘルス不調や離職に繋がりかねないため、企業は適切な対策を講じる必要があります。
今こそ日本は待ったなしの「感情労働者の権利保護」に乗り出すべきです。海外では既に感情労働者権利保護法制が施行されている国もあります。日本も早期に感情労働者の人権を守る手段を講じるべきでしょう。
小売業・サービス業界では「お客様は神様です」という言葉を耳にします。いうまでもなく昭和の国民的歌手・故三波春夫さんの言葉として今なお残る名言です。
これって実はお客様の立場を肯定するのが本意ではなく、サービスを提供する側の心構えを説いた言葉であるのです。客の立場が強いことを表現するのに、しばしば使われてきたフレーズ「お客様は神様です」が、店員や従業員らが顧客から無理難題を言われたり、暴言を浴びせられたりするカスハラが問題視される現在、よく引き合いにされる言葉です。
このフレーズは昭和36年ごろ、三波春夫氏がある地方公演で口にした言葉が発端でした。会場がお客さんの熱気に包まれる中、司会の方から「お客様をどう思いますか」と聞かれたとき、「お客様は神様だと思いますね」と答えたのです。客席が大いに盛り上がったことから、その後も各地のツアーの主催者から同じ発言を求められるようになったそうです。
やがてトリオ漫才のレツゴー三匹さんがそれを真似る様になって、世間で流行するようになったのですが、三波春夫氏の真意とはかけ離れ、「お客様は神なんだから、何をされようが我慢してつくしなさい」というような間違った解釈で広まっていきました。
三波春夫氏は生前にこの言葉の真意について説明していますが、これは自分の歌を、芸を完璧な形でお客様と視聴者にお届けしなければならないという心構えを表したものでした。
・・・なので、お客様は神様ではないのです。つまり客と店員との関係に上も下もありません。『いらっしゃいませ』や『ありがとうございます』といった感謝の気持ちは表現したとしても、私はあなたの下僕ですという考え方ではありません。嘗て大馬鹿野郎が居て、偶々どこかで客になった時に『俺は神様扱いされて当然だ』と思ったのでしょうね。
日本人というのは実に不思議な民族で、「言葉」が出来ると俄然解決に躍起になるのです。言霊信仰の影響なのでしょうか。ようやく行政がカスハラ排除に向けて、本腰を入れ始めたような気配がするので少しは良くなるとは思いますが、客商売をしていると、相手はまるで店員を下僕のように扱います。金を出すのだから、言うことを聞くのが当たり前だと思っているのです。これって拝金主義の成れの果てとでも言えるでしょう。
一つ気が付いた事ですが、客を「お客様」と呼んでしまう慣習です。誰も不思議に思わないと思いますが、実はこの言葉、二重敬語になっています。お客様の「お」は丁寧語ですので、これだけで客という存在を丁寧に表現しており、さらに「様」を付けることで、最上級の敬意を表現しているのです。食事でも充分通じますが「お食事」という人もいますね。「お」を付けることで丁寧な物言いになるわけです。間違っても「お食事様」と言いません。
子供達には「人権とは尊いものだ」と常日頃から教えていきたいですね。
今日もいい日になる様に
いつでも笑って優しくね!
ぽぽぽ、ぽぽぽ、ぽ~ん!
今日もいい日になる様に
下記のバナーをプチッとして当ブログの順位を確認して頂ければ嬉しいです。皆様方にクリックして頂きますと当ブログのポイントが上がります。皆様方のご支援は管理人にとって大きな励みになりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ブログ人気ランキング(ソフトテニス)



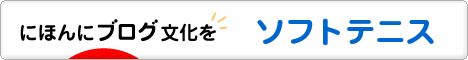
0 件のコメント:
コメントを投稿