承認欲求とは、他者から認められたい、評価されたいという、人間が誰しもが持つ基本的な心理的欲求のことです。アブラハム・マズローの「欲求5段階説」では第4段階の欲求として位置づけられており、社会生活を送る上で重要ですが、強すぎると人間関係の悪化や精神的な負担につながることもあります。
【承認欲求の基本的な側面】
①.
他者からの承認
「褒めてほしい」「尊敬されたい」といったように、他者から肯定的な評価や受け入れを求める欲求です。
②.
自己承認
自分の能力や価値を自身で認めたいという欲求も含まれます。
【承認欲求が働く背景と影響】
①.
社会的な存在であること
人間は社会的な動物であり、他者との関わりの中で自己の存在意義を感じるため、承認欲求が生じます。
②.
自己肯定感との関連
自己肯定感を高めるための基盤となる欲求の一つです。
③.
現代社会での顕著化
SNSの普及などにより、他者からの「いいね」やコメントなどを通じて、より直接的に承認を求め、表現する傾向が見られることがあります。
【承認欲求が強すぎるときの悪影響】
①.
ネガティブな人間関係
他人より評価されたいという思いから、自慢話が増えたり、同僚を過度にライバル視したりすることで、人間関係が悪化することがあります。
②.
精神的な負担
常に他者の目を気にしすぎてしまい、不快な思いをしたり、不安に苛まれたりすることがあります。
③.
失敗に対する過度な落ち込み
承認を得られないと感じた時に、モチベーションが著しく低下し、落ち込みやすくなることがあります。
【承認欲求との付き合い方】
①.
自己承認を重視する
他者の反応に過度に依存せず、自分自身の価値を認め、成長を喜ぶことを意識しましょう。
②.
自分の気持ちに正直になる
人に迷惑をかけない範囲で、自分の好きなことややりたいことに正直に行動する経験を重ねることが大切です。
③.
人間関係を良好に保つ
コミュニケーションを積極的にとり、良質な人間関係を築くことで、自然な形で承認欲求が満たされることがあります。
上述のとおり、承認欲求とは、他者から認められたいという強い欲求を指します。この欲求は、他者の期待に応えたり、評価を受けたりすることにより、自己価値を確認しようとする心理的な傾向です。
承認欲求が過度に強くなると、他者の評価に依存するあまり、自己肯定感が低くなる場合があります。適度な承認欲求は自己成長を促しますが、過度になると自己評価が他者に左右され、精神的な不安定さを招くこともあります。
社会生活の中で他人から認められたい、自分を理解してもらいたいという承認欲求は、子供から大人まで誰でも持ち合わせています。幼い子どもや小学生が「見て!」と大人に何度もアピールするのは、親や先生など大人たちに「すごいね」と褒めてもらいたい、自分を高く評価してもらいたいという気持ちがあるからです。
一方、自己顕示欲とは、人気者になりたい、自分の存在を周囲にアピールしたい、大勢の人から注目されたい欲求のことです。一方の承認欲求は他者から自分の存在価値を認められたいという欲求です。自己顕示欲は、他人からの注目を得られれば自分の欲求が満たされるという自分中心的な要素を持ちますが、承認欲求は他者中心的な考えになっています。
現代人は明らかに承認欲求が高くなってきています。その理由には下記の3つが考えられます。
(1)
時代背景
ひと昔前の日本社会における社会的なステータスは、有名大学を卒業して上場企業メーカーに就職して昇進し、高い給料をもらうというものでした。これが他人から認められる最も分かりやすい指標だったのです。しかしながら現代は、大企業の1人よりも、新しい価値を提供するベンチャー企業や実力ある個人が活躍する時代となっています。肩書きや地位ではなく、人間性の部分が評価される社会に変わってきたのです。そう! 昔は東大等の有名大学の学士を持っていれば、充分に承認欲求が得られたのです。でも今はその時代ではありません。要は実力、人間性の世の中に変わっていったのです。
(2)
SNSの時代
スマホ時代といわれる現代、子供から大人までがSNSで共通の趣味や同じ目的の下に集まる人たちとつながり、自分と同じように考えている人や、自分の悩みに共感してくれる人がいることで、自分の存在が認められていると実感します。また個人の発言にコメントが付く時代である昨今、「影響力がある」と他者から評価されたい欲求に依存しやすくなるため、SNS上での評価に振り回されやすくなるのです。
(3)
家庭環境
現代人に承認欲求が強い人が増えた原因に、幼少期の家庭環境があるとされています。両親から褒められずに幼少期を過ごした人は、自分の価値を信じられないまま大人になるのです。そのため他人から認められたいという承認欲求が強い人になるといわれています。先日のブログ記事でも書きましたが、子供に対する親のネグレクトは厳禁です。赤ちゃんから小学生までの時期に、周囲の大人たちに褒められず成長すると、「自分がやりたい物事に取り組んで承認欲求を満たす」方法が持てなくなるといわれています。共働きが当たり前の現代、多忙な大人たちは子供と向き合う時間が少ないものです。その結果、親の承認を受けられずに日々を過ごす子どもたちが増えてきているのです。
STAP(Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency、刺激惹起性多能性獲得細胞)なるものが発見されたと2014年1月に理化学研究所が発表し、たいへんな騒動になった記憶は新しいと思います。その渦中にいたのが小保方晴子氏です。この騒動については、毎日新聞科学環境部記者の須田桃子氏が2015年1月に文藝春秋から上梓した『捏造の科学者―STAP細胞事件』(第46回大宅壮一ノンフィクション賞受賞)で真相が詳しく解明されています。本件を決めつける訳ではありませんが、科学の世界で捏造、その根底にあるものは異常な承認欲求であると思います。
因みに中国では捏造を含めた研究不正によって健康被害が生じた場合、最大で死刑が言い渡されることもあります。日本を含めほとんどの先進国では、学術界の不正行為を捏造、改竄、盗用の3つと定義しており、捏造は科学における不正行為とみなされます。2014年に文部科学省は捏造、改竄、盗用の3つを「特定不正行為」と命名しています。Youmeiも科学者の端くれではありますが、43件の発明特許に於いてもこの様な不正行為はしていません。Youmeiの特許出願リストです。
https://drive.google.com/file/d/1xmBMR6BHEIp81CTpZYXNQLUCdOL2uZIt/view?usp=sharing
科学の世界での捏造は下記の3つが実例として有名です。
①.
STAP細胞事件 (2014年)
理化学研究所で発表されたSTAP細胞の論文で、データや画像が捏造・改ざんされていたことが発覚し、研究が撤回されました。
②.
ファン・ウソクのES細胞論文不正 (2004年)
韓国の黄禹錫(ファン・ウソク)氏が発表したヒトES細胞の論文が捏造であったと認定され、撤回されました。
③.
アンドリュー・ウェイクフィールドのMMRワクチンと自閉症の関連論文 (1998年)
イギリスの医師アンドリュー・ウェイクフィールドが発表した、MMRワクチンと自閉症に関連があるとする論文は、後に捏造であることが明らかになり、撤回されました。
YoumeiはYouTubeチャンネルのアカウントを持っています。
https://www.youtube.com/user/youmei5555
再生回数5,157,123
views、フォロワー3,120名もいらっしゃってご評価を頂いた事は感謝しております。このチャンネル創設当時は、フォロワー数や再生回数、いいね!の回数等を異常なほど気にしておりました。その頃は小遣い程度でしたが、広告収入も頂いておりましたが、今は広告を出さない設定に変えています。今、思えばその頃の自分の承認欲求は異常に高かったのだと思います。そうですねぇ~、妻と結婚してから承認欲求は大分薄れましたね。妻にも感謝です。
今日もいい日になる様に
いつでも笑って優しくね!
ぽぽぽ、ぽぽぽ、ぽ~ん!
今日もいい日になる様に
誰かに笑顔でありがとう!
下記のバナーをプチッとして当ブログの順位を確認して頂ければ嬉しいです。皆様方にクリックして頂きますと当ブログのポイントが上がります。皆様方のご支援は管理人にとって大きな励みになりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ブログ人気ランキング(ソフトテニス)



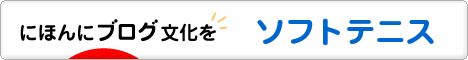
0 件のコメント:
コメントを投稿