子育てにおける過干渉とは、子どもの自主性や自立性を尊重せず、親の価値観や意志を押し付けたり、生活のあらゆる面に介入したりする子育てスタイルです。これは子どもの意思を無視して行動をコントロールするため、子どもは大きなストレスを感じ、自分で考える力や自己肯定感、主体性が育ちにくくなるなど、自立に必要な能力が損なわれる悪影響があります。過干渉は、親の不安や子どもの将来への責任感、自己肯定感の低さなどが原因で起こりやすく、親自身が気づきにくい場合もあります。過干渉な子育ての特徴として以下の事項が挙げられます。
1) 子どもへの過度な介入
子どもの生活、学業、友人関係など、あらゆる面に口を出し、先回りして過剰な対策を取る。
2)
親の意志の優先
子どもの意見や希望を無視し、親の価値観を押し付けたり、行動を細かくコントロールしたりする。
3)
子どもの主体性を奪う
子どもが自分で考えて決断する機会を奪い、自発的に何かをする機会を奪ってしまう。
4)
否定的な関わり方
子どもの発言を遮る、好みや選択を否定する、アドバイスを命令と捉えられるような言い方をする。
5)
完璧主義
親が完璧主義で、親自身の理想を子どもに重ね、結果を重視しすぎる傾向がある。
この様な過干渉は子どもへの悪影響を及ぼすのは明らかです。
1)
自立心や主体性の低下
自分で考える機会が少なくなり、自分で判断したり行動したりすることが苦手になる。
2)
自己肯定感の低下
自分の考えや行動が尊重されない経験から、自己肯定感が低くなる。
3)
ストレスの増加
親のコントロールによって子どもの自由が奪われ、ストレスを溜め込みやすくなる。
4)
社会適応の困難
自分で決めることが苦手で、指示がないと思考が停止してしまうなど、社会に出て苦労する可能性がある。
親が過干渉になる理由もそれなりにはあると思います
1)
親の不安や心配
子どもの将来への責任感や「こうしなければならない」という焦燥感が原因で、子どもを過度にコントロールしようとする。
2)
親の自己肯定感の低さ
他者の評価を気にし、子どもの失敗が自分自身の評価を下げることを恐れて子どもをコントロールしようとする。
3)
コントロール願望
「親の思い通りに子どもを育てたい」という親の願望が根底にある場合がある。
過干渉と比較されることに「過保護」があります。どちらも親御さんが子ども対する“関わりすぎ”があるという点は似ています。
「過保護」は文字通り、親による子どもの保護が過度になっていることを指します。子どもの意志や判断・選択を過度に重視し、親がそれに従う場合(いわゆる、「甘やかし」)は過干渉と関係性が逆になっているため、かなり異なっています。
しかし、保護を理由に親の意思に子どもを従わせる(例えば、子どもを悪影響から守るために適切な挑戦や冒険をさせない、子どもが自分でやりたいことも親がやってあげる、禁止や制限が多くなる)タイプの「過保護」もあり、この場合は目的が保護なだけで、メカニズムとしては過干渉と似ています。
過干渉な保護者は、自身の意思に子どもを従わせるので、単に関わりの量が多くなるだけではなく、関わりの内容のほとんどで保護者が子どもを否定し、誤りを指摘し、お説教するということになってしまいます。反対に、親が子どもの話を聞く、受け止める、認める、褒める、勇気づけるという関わりがなくなってしまいます。例えば、学校や習い事で子どもがかんばっていたとしても、親の望む結果に届いていないと、「次はもっと頑張りなさい」「だから言ったでしょう」という反応だけを親はしてしまうかもしれません。否定や指摘ばかりで、話を聞いてもらえない、受け止めてもらえない、認めてもらえない、褒められない、勇気づけられないという経験は、複合して大きな悪影響を生むことにもなります。
更に、子どもへのアドバイスという形を表面的にはとりながらも、実質は命令、禁止、指示になってしまう事があります。一般的にアドバイスは「……してみるのはどう?」といったように、アドバイスを受ける側が判断・選択する余地を残すものです。しかし、アドバイスと言いながらも、「……しなさい」という命令口調であったり、あるいは口調はアドバイスの形をとっていても、これまでの親子関係の中で従わないことは許されないことが続いていたりする場合は、実質的に命令となります。そうなると、子どもが判断、決定する余地は残されておらず、さまざまな悪影響があります。
幼少の頃の親の過干渉が大人になって受ける悪影響で、一番困るのが人間関係がうまくいかないリスクが高まる事です。「どうせ私なんて」と友人を作ることに臆病になってしまったり、自分の気持ちを伝えることがうまくできなかったりすることもあるかもしれません。反対に、家庭で親から支配されている気持ちを晴らすために、友達関係では誰かを支配しようとする子どももいて、その場合も友達関係でトラブルを抱えることもあります。
更に最もヤバイのが、過干渉により何も言わなくても保護者のかたに助けられてきた経験から、他の人に助けを求めたり頼ったりするのが苦手になりやすいです。そのため、受け身の姿勢になり人との距離感がつかめず、結果的に他人と深い関係をつくりにくくなってしまうかもしれません。「察してくれないならいいや」と、不信感を持ち、殻に閉じこもりがちになることもあります。保護者の方々は、お子さまのヘルプを先読みして助けるのではなく、助けを求めてくるまで待つ事で、お子さまが自分の意思をしっかりと伝えられる様になります。
機会があれば皆様方も過干渉についてご一考されてみて下さい。
今日もいい日になる様に
いつでも笑って優しくね!
ぽぽぽ、ぽぽぽ、ぽ~ん!
今日もいい日になる様に
誰かに笑顔でありがとう!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ブログ人気ランキング(ソフトテニス)


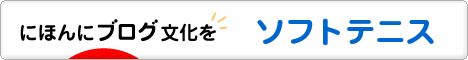
0 件のコメント:
コメントを投稿