「選択で未来が変わる」とは、日々の小さな選択の積み重ねが、望む未来を形作っていくという考え方です。未来はあらかじめ決まっているものではなく、今の選択が未来の展開を決定するということです。日常のあらゆる場面での選択を意識し、新しい選択をしたり、より良い選択を習慣化したりすることで、未来を自分自身で変えていくことができるという意味合いです。
①.
選択の連続が未来を創る
私たちは日々、朝起きてから寝るまで、数え切れないほどの選択をしています。何をするか、何を食べるか、どう行動するかといった一つ一つの選択が、その後の展開を決定し、未来の自分を作っていきます。
②.
意識的な選択の重要性
意識的に「いつもと違う」選択をしたり、より良い選択を意識したりすることで、新しい発見や気づきが生まれ、未来を変えるきっかけになります。例えば、「毎日10分だけストレッチをする」といった小さな選択を習慣にすることが、未来の健康につながります。
③.
未来は「自分で決める」もの
未来は誰かに決められるものではなく、自分で決めるものです。今の状況に不満があるなら、「変わる」という選択をすることで、未来の自分を変えることができます。
④.
「未来を創る」ことは「行動する」こと
自分の望む未来をただ予測するのではなく、自らの行動を通して形にしていくことが、「未来を創る」ことです。そのために、日々の選択をより良いものへと変えていくことが重要です。
【個人の人生における自己決定】
人は、キャリア、人間関係、日々の習慣など、多くの局面で選択を繰り返しています。
①. キャリアの選択
どの仕事に就くか、いつ転職するかといった決断は、その後の働き方や生活の質を大きく左右します。
②. 習慣の選択
毎日何をするか(勉強する、運動する、休むなど)という小さな選択の積み重ねが、健康やスキルアップといった未来の結果につながります。
③. 自己肯定感の向上
自分で選び、自分で決める経験を重ねることは、自己肯定感や自己統制能力を高め、より良い未来を築くための土台となります。
【「バタフライ効果」に見る連鎖反応】
バタフライ効果とは、ごく小さな出来事が、時間とともに広がり、予測不可能な大きな変化をもたらすというカオス理論の概念です。
①. 些細な決断が大きな結果に
例えば、ある日たまたま立ち寄った場所で出会った人との会話が、後に人生を左右するような仕事のチャンスにつながることがあります。
②. 物語を形作る
日常の何気ない選択が、やがて壮大な物語の伏線となり、思いがけない結末を引き起こす、といったように使われることもあります。
【集団や社会における影響】
個人の選択だけでなく、企業や社会全体での選択も未来を変えます。
①. 企業の選択
企業の経営判断や環境への配慮といった選択は、その企業の将来性や社会への影響を決定します。
②. 社会の選択
どの様な社会を目指すかという集団的な選択は、地球環境や人類の未来そのものに影響を与えます。
【心理学的な視点】
心理学の一分野である選択理論心理学では、人間の行動は自らの選択によるものであり、感情や生理反応もその選択と密接に関係していると考えます。
①. 自らの選択に責任を持つ
自分の行動や結果をコントロールする能力を養うことで、ストレスへの対処や精神的な強さが養われます。
②. 後悔の心理
選択肢が多すぎると、決断後に「もっと良い選択があったのでは」と後悔する「選択のパラドックス」という心理作用も存在します。
「選択で未来が変わる」という言葉は、私たちの意志や行動が、個人的な人生から社会全体に至るまで、さまざまなレベルで未来を形作っていくという深い意味を持っています。日々の決断を意識的に行うことの重要性や、過去の選択が現在の自分を作っているという事実を改めて考えさせてくれる言葉と言えるでしょう。
「手段の目的化に注意」と言った事は良く言われています。しましながらそこで挙げられている「本来の目的」の奥にも実は「究極の目的」と言えるものがあります。そして「究極の目的」から見れば「本来の目的」も手段でしかなかったりする、そんな事もよくあるのです。どの「時間軸の範囲」にフォーカスするかで、手段は目的になったり、目的は手段になったりします。
上図の「中間の目的B」の位置が分かりやすいと思います。そして、現実にも同じ様なケースがあるハズです。これが本当の目的だと掲げたものも、実は究極の目的の手段だったりすることは割とよくあるのです。「手段の目的化」は、どの時間軸を見るかのズレによって起こると思います。「時間軸の視野」と言ってもいいかもしれません。どこからどこまでの範囲にフォーカスするか、その範囲設定で中間地は手段にも目的にもなるのです。・・・であれば「現在地」と「究極の目的」の二点を見定めておけば良いかと言えば、そんな事もないのが興味深いです。勿論この両者は大切なのですが、人それぞれに持つ価値観やフェーズ感によって「クリアに見える時間軸の視野」はきっと異なっているハズです。時間軸の視野が相手と異なっている時に完全に一方の見ている世界観に合わせるのはかなりの無理があります。お互いの視野から一歩ずつ相手に近づいて歩み寄りをするから共通認識に近づけるのではないかと考える訳です。
40年前になりますが、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(Back to the Future)が公開されました(当時、Youmeiは25歳)。スティーブン・スピルバーグ製作総指揮の下、監督のロバート・ゼメキスがボブ・ゲイルと共に脚本を作成し、マイケル・J・フォックス、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、クリスピン・グローヴァー、トーマス・F・ウィルソンらが出演しています。
このお話しですが、1985年、高校生のマーティ・マクフライは、近所に住む科学者のエメット・ブラウン博士(通称ドク)が愛車デロリアンを改造して開発したタイムマシンの実験を手伝うが、誤作動で1955年の世界にタイムスリップします。タイムマシンは燃料切れで動かなくなってしまいました。困ったマーティは1955年のドクを探し出し、事情を説明して未来に戻る手助けをしてもらうことになりますが、その過程で若き日の両親の出会いを邪魔してしまいます。このままでは自分が生まれないことになってしまうため、マーティは未来に戻る前になんとか両親の仲を取り持とうと奮闘するのです・・・・、以下省略。
抜群のセンスで作成されたSF映画ですが、この話こそ「貴方の選択で未来が変わる」事を象徴しています。この映画はPart2、Part3の続編まであるのでが、本当に傑作だと思います。
どんな未来が来るのか誰も解りません。何故ならば未来への時間軸は無限に存在するからです(パラレルワールドは実在すると思います)。だから未来を決めるのは今の自分なのです。人それぞれ今の何を選択するのかによって未来は変わります。子供達にもこの時間軸の定義を理化して貰って、未来に向かって良い選択(最善手です)をして欲しいと考えています。
今日もいい日になる様に
いつでも笑って優しくね!
ぽぽぽ、ぽぽぽ、ぽ~ん!
今日もいい日になる様に
誰かに笑顔でありがとう!
下記のバナーをプチッとして当ブログの順位を確認して頂ければ嬉しいです。皆様方にクリックして頂きますと当ブログのポイントが上がります。皆様方のご支援は管理人にとって大きな励みになりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ブログ人気ランキング(ソフトテニス)



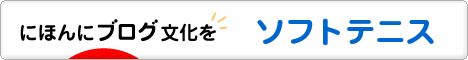
0 件のコメント:
コメントを投稿