「科学」とは多くの観察と観測、実験結果に支えられた、変わり続ける知識の体系です。 例えば自然科学には、物理、化学、地学、生物学など様々な分野が含まれます。これらの分野の知識の体系が自然科学になります。
「科学」は、広義にはおよそあらゆる学問の領域を含むものであるが、狭義の「科学」とは、とくに自然の事物、事象について観察、実験等の手法によって原理、法則を見いだすいわゆる自然科学及びそれに係る技術の事を言います。
「科学」は、世界や現象を研究する際、経験的な観察や実験によって検証できる体系化された合理的な認識、またはその成果としての知識の体系です。その主要な特徴として、同じ条件で同じ結果が得られる「再現性」や、観察・実験結果に裏付けられた「客観性」が挙げられます。科学は、研究対象によって自然科学、社会科学、人文科学などに分類され、これらの知識体系を指します。
【科学の主な特徴】
①.
実証性(経験性)
経験的な観察や実験によって検証できることが重要です。
②.
再現性(再生産性)
同じ条件であれば、いつ・どこで・誰が調べても同じ結果が得られる必要があります。
③.
客観性
主観ではなく、事実や事実に裏付けられた客観的な認識に基づきます。
④.
論理性と体系性
得られた知識は論理的に一貫しており、体系化されています。
⑤.
普遍性
科学的法則は、例外なく常に妥当する性質を持つことがあります。
【科学の分類】
①.
自然科学
物理学、化学、生物学など、自然現象や自然界の法則を扱う分野です。
②.
社会科学
経済学、心理学、社会学など、人間社会や社会現象、人間集団の行動を研究する分野です。
③.
人文科学
歴史学、文学、芸術など、人間の内面や生み出したもの、文化を扱う分野です。
【科学の語源と歴史】
①.
「科学」という言葉は、ラテン語の動詞「scio(知る)」に由来する「science」を語源とする、日本で明治期に造られた言葉です。
②.
近代科学の成立は17世紀頃とされ、科学者による体系的な研究が始まりました。
この様に「科学」は単に知識を蓄積するだけでなく、その知識がどのように得られ、どのような性質を持つのかという点に特徴があります。
Youmeiの専門は物理化学です。その中でも界面化学の分野に於いては水を得た魚の様に活発な思考が出来ます。仕事が医薬品の研究開発職でしたから、薬学、薬剤学、分析化学、統計学の分野も得意です。但し、生物学、薬理学の方は苦手です。薬理の実験ではin vivoは全く出来ません。薬理の実験はやったとしてもin vitroのみでした。何故ならばin vitroとは、「試験管内試験」という意味で、試験管を用いた試験であるのに対して、in
vivoは、「生体内試験」という意味で、動物などの生体内で直接投与したりする試験だからです。研究所にはマウス、モルモット、ラット、ビーグル犬の飼育施設と実験施設がありましたが、約30年の間、そこの場所に出向いたのはほんの1回だけでした。実験に生き物を使うのは気持ちの上でも自分には出来ませんでした。
「科学」の仕事は探偵と非常に良く似ています。どちらも「なぜ・なぜ」で始まるからです。「なぜ・なぜ」は、発生した問題の原因を深掘りし、根本的な原因(真因)を特定するための分析手法である「なぜ・なぜ分析」を指します。トヨタ生産方式から生まれ、問題の表面的な原因だけでなく、背後にある根本的な要因を突き止めることで、同じ問題の再発防止につなげます。英語では「5Whys」とも呼ばれ、一般的に「なぜ?」を5回繰り返すことで真因に到達すると言われています。
「科学」の分野で新発見(発明)をするステップは、上のスライドによく似ています。探偵職も然りですが、先ずは「何故?」と言った疑問を持ち、そのメカニズムを解明していく仕事になります。やみくもに考えても簡単に答えが出るものではありません。やり方は探偵が推理するのと同様に仮説検証を繰返して成就するものなのです。
一般に仮説検証とは、ある現象や課題に対して「〇〇だからこうなるはずだ」と言った「仮説」を立て、その真偽をデータや事実に基づいて確認する一連のプロセスです。ビジネスでは、新規事業開発や市場分析、マーケティングなどで、仮説を繰り返し検証し、より確かな事業開発や成果につなげるために不可欠な思考法です。
【仮説検証の基本的な考え方】
①.
仮説の設定
現状の観察・分析に基づき、解決したい課題や現象に対して「こうすれば〇〇が達成できるはずだ」といった「仮の答え(仮説)」を設定します。
②.
検証方法の設計
設定した仮説が正しいかどうかを確かめるために、どのようなデータを収集し、どのような手法で検証するかを具体的に設計します。
③.
検証の実行
アンケートやインタビュー、実験、市場テスト(MVP開発など)といった手法を用いて、設計した検証を実行します。
④.
結果の分析と改善
収集したデータや結果を分析し、仮説が正しいかどうかを判断します。間違っていれば仮説を修正し、正しい場合は次の改善策や事業開発に活かします。
Youmeiはこの手法をも用いて43件の発明を特許と致しました。
https://drive.google.com/file/d/1xmBMR6BHEIp81CTpZYXNQLUCdOL2uZIt/view?usp=sharing
一番思い出がある発見は非イオン性界面活性剤による親油性物質の可溶化をする際、ラングミュアーの吸着等温式に従った考察が出来ると言った知見を限外濾過法の手法を使って導き出した事です。ラングミュアーの吸着等温式とは、固体表面が均一で、吸着分子間には相互作用がなく、単分子層しか形成されないと仮定して、吸着量と分子の圧力(または濃度)の関係を表した数式です。この式では、固体表面の吸着点に分子が吸着し、単分子層が形成されれば吸着が終了すると考えます。
【ラングミュアの吸着等温式の仮定】
①.
均一な吸着点
固体表面の分子吸着活性点はすべて等しく、吸着する分子も同じエネルギーで吸着すると考えます。
②.
単分子層吸着のみ
吸着した分子は、表面の吸着点に単分子層としてしか存在しないと考え、多分子層吸着は起こりません。
③.
吸着分子間の相互作用がない
吸着した分子間には相互作用がないと仮定します。
ラングミュアーの吸着等温式は、一定温度の条件下で、気体が固体表面に単分子層(一層)を形成しながら吸着する現象をモデル化したものです。化学者アーヴィング・ラングミュアーが1916年に発表しました。ラングミュアーの吸着等温式は、吸着平衡状態において、表面の被覆率(吸着サイトのうち分子で占められている割合)を気体の圧力(または溶液の濃度)との関係で示します。
V = a b P / (1 + a P)
V:吸着量
P:分子の圧力
a, b:特定の物質と固体に対する吸着の特性を表す定数
最近になって若手の同姓同名の研究者がいらっしゃる様で、検索結果に幾らかノイズが入りますが、Youmeiが携わった研究論文です。
本日、一番言いたかった事は因果応報です。「因果応報」とは、仏教に由来する言葉で、過去の善い行い(原因)には善い報い(結果)が、悪い行い(原因)には悪い報い(結果)があるという仏教の教えや、その道理を指します。現代では、特に「悪い行いに対する悪い結果」という意味で使われることが多いです
手品に種があるが如く、不可解な物事が発生した場合でも必ず原因があります。好奇心と探求心を持って常に「なぜ・なぜ分析」を心掛けて下さい。必ず良い答えが得られますよ。
今日もいい日になる様に
いつでも笑って優しくね!
ぽぽぽ、ぽぽぽ、ぽ~ん!
今日もいい日になる様に
誰かに笑顔でありがとう!
下記のバナーをプチッとして当ブログの順位を確認して頂ければ嬉しいです。皆様方にクリックして頂きますと当ブログのポイントが上がります。皆様方のご支援は管理人にとって大きな励みになりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ブログ人気ランキング(ソフトテニス)




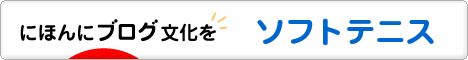
0 件のコメント:
コメントを投稿