「怒鳴る」とは、感情的に大声で叫ぶ事、または激しくしかりつける事を意味します。より詳しく説明すると「怒鳴る」とは、
1.
怒りや不快感などの感情が高ぶって、大声で叫ぶ事。
2.
相手を叱責する際に、大声で叱咤する事。
「怒鳴る」は、単に大きな声で話すだけでなく、感情的な要素を伴う点が特徴です。また、相手を威嚇したり、恐怖を与えたりする意図が含まれます。
頻繁に怒鳴る指導者・教師・先生は三流です。指導がうまくいかない時に、怒鳴ってなんとかするというのはよくないやり方です。指導者として、脅すような言動は当然よくありません。子どもたちへの指導が難しくなってきており、ついつい教師は手詰まりになりがちです。思ったように指示通りの行動ができないとき、怒鳴ってしまうことがあります。場合によっては一喝をいれる場面も必要でしょう。しかしながら、一貫して強面の指導者が存在する事は必要悪だと思います。
この「怒鳴る」という方法をずっとやり続けていると、子供たちにも耐性ができてきます。指導者には実質的に子供に対する懲戒方法がありません。そうなると、子供は「なーんだ、指導者って怒鳴ることぐらいしかできないんだ」となって、怒鳴られてもそれをやり過ごせばいいという知恵がつきます。
怒鳴る事でとりあえず何とかなると指導者が味をしめると、指導に工夫がなくなり、指導者としての成長の妨げになります。「自主性がない」と言っては怒鳴って、自主的に子供が動くと「勝手な行動をするな」と怒鳴ってはいる指導者はいませんか?
きっと指導者が怒鳴らずとも子供たちがしっかりと育っている集団もあるハズです。「怒鳴り癖」のついてしまっている指導者は、そういった集団のやり方を学ぶことは多いと思います。
怒鳴るも一つの指導方法ではあるとは思いますが、いつまでもそれで辻褄を合わせようとすると子供たちは委縮したり、「また怒鳴る」と心の中で嫌気がさしてきたりします。特に最近の子供は怒鳴られたり、怖い顔をされると委縮しすぎて、酷い場合にはそれで終わってしまうケースもあります。「怒鳴る」は間違いなく三流です。もし、百歩譲って、どうしても怒鳴らなければならないなら、個人を怒鳴るより全体を怒鳴る方が良いと思います。そしてま万一にも怒鳴るとしても、次の事は気を付けて下さい。
①
効果的に
②
要所で
③
少ない目にすることを目指して
④
冷静さをもって
「怒鳴る」「脅す」と「叱る」「諭す」は、違います。「怒鳴る」「脅す」は指導者側の都合である場合が多く、「叱る」「諭す」は子供たち寄り添った指導であると考えています。怒鳴るのは怒鳴らなければならない状況を作った自分自身に責任の半分はあると考えましょう。怒鳴ることは決して良くないことを自覚しながら怒鳴りましょう。そして、だんだん「怒鳴る」から「叱る」「諭す」~「ほめる」に変換していけるように心がける必要があります。怒鳴らなくてもいい方策をどんどん取り入れて、指導者も子供も嫌な気分をせずに毎日を過ごせるようになるように、成長していかねばなりません。
勿論ですが大人の関係も然りです。
ある小学生の子供がネットに書き込んでいました。
「父親は母親をグーで殴りました。母親は一時期家をでました。もう2回めです。
視界にはいれば怒鳴り合っています。つかれます」。
賢明な大人の皆様方へ どうか子供の前での怒鳴りあいは絶対に止めて下さい。自己抑制出来ない大人は恥ずかしいですよ。
今日もいい日になる様に
いつでも笑って優しくね!
ぽぽぽ、ぽぽぽ、ぽ~ん!
今日もいい日になる様に
下記のバナーをプチッとして当ブログの順位を確認して頂ければ嬉しいです。皆様方にクリックして頂きますと当ブログのポイントが上がります。皆様方のご支援は管理人にとって大きな励みになりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ブログ人気ランキング(ソフトテニス)


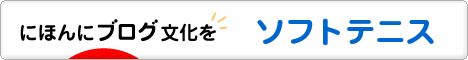
0 件のコメント:
コメントを投稿